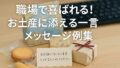スーパーでよく見かける食品トレーの回収ボックス。
ところが卵パックを入れようとすると「回収対象外」と書かれていて、不思議に思ったことはありませんか?
普段何気なく捨てている卵パックですが、実はそこには複雑な事情が隠れています。
他のプラスチック容器にはない“回収されにくい理由”が存在し、自治体やスーパーの回収ルールにも大きな差があるのです。
なぜ卵パックだけが例外扱いされるのか、素材や衛生面の問題、リサイクルの仕組みの違いを知ると、その背景が見えてきます。
この記事では、その理由を丁寧に解説するとともに、正しい捨て方や実際に自治体での取り扱いの違い、さらに家庭でできる再利用の工夫まで紹介します。
「捨てる」だけで終わらせず、暮らしの中で少し工夫することで環境への負担を減らすことができる――そんな視点を持っていただける内容にまとめました。
卵パックはなぜ回収されないのか?

食品トレーと何が違う?素材と衛生面の問題
卵パックは、見た目は食品トレーと似ていますが、素材や形状が大きく異なります。
多くの卵パックはPET(ペット)素材で作られており、食品トレーに多く使われているPS(ポリスチレン)とはリサイクルの仕組みも性質もまったく違います。
PETは透明度が高く軽量で強度もありますが、その分リサイクル工程が複雑で、専用の設備や工程が必要とされます。これに対し、PSはリサイクルルートが比較的確立されているため、食品トレーとして広く回収可能なのです。
さらに卵は中身が割れると黄身や殻の汚れが付きやすく、乾燥してこびりつくと洗浄にも手間がかかります。
そのため衛生的なリサイクル処理が難しいことも大きな理由のひとつです。
加えて、卵パックは仕切りが多く立体的な形状をしているため、圧縮や運搬の効率も悪く、回収コストが高くなりやすいという課題もあります。
こうした素材・形状・衛生面の要因が重なり、卵パックが食品トレーと同じように簡単には回収されない現状につながっているのです。
卵パックと食品トレーの違い(比較表)
| 項目 | 卵パック | 食品トレー |
|---|---|---|
| 主な素材 | PET(ペット樹脂) | PS(ポリスチレン) |
| 見た目 | 透明が多い | 白や黒の不透明が多い |
| 主な用途 | 卵の包装 | 肉・魚・惣菜などの包装 |
| 衛生面の問題 | 卵の殻や黄身の汚れが付きやすい | 汚れはあるが洗浄しやすい |
| リサイクルルート | 全国的に整備されていない | 多くのスーパーで回収ボックス設置済み |
| 回収対象 | 一部のスーパーやコープのみ | ほとんどのスーパーで対象 |
| 再利用のしやすさ | 小物収納・工作に活用できる | ガーデニングや工作に活用されやすい |
地域やスーパーごとの回収ルールの違い
自治体によって「卵パックは資源ごみ」「燃えるごみ」など扱いがバラバラです。
中には透明なPET製卵パックのみを資源ごみとして認める自治体もあれば、すべてを燃えるごみに回しているところもあります。
また、スーパーでも食品トレーは回収しても卵パックは対象外、というケースが多く見られます。
例外的に一部店舗では専用ボックスを設置していることもありますが、全国的に見るとまだ少数派です。
このようにルールが統一されていないのは、回収後の処理ルートが確立していないことが大きな原因であり、自治体ごとの処理設備や契約業者の違いも影響しています。
消費者にとっては分別方法がわかりにくく、混乱の元になっているのが現状です。
リサイクル工程での課題とコスト面
卵パックは軽くてかさばるため、運搬コストが高くなりやすい素材です。
大量に集めてもリサイクルとしての価値が低く、コスト面で回収が難しいという背景もあります。
さらに、汚れや破損のある卵パックを洗浄するためには水やエネルギーが余分に必要になり、その分環境負荷やコストが増大します。
再生品としての需要も限定的で、集めたとしても効率よく循環させにくいという問題も抱えています。
結果的に、コストと労力のバランスが取れず、回収活動が広がりにくい要因となっているのです。
卵パックの正しい捨て方

自治体ごとの分別ルールを確認する
まずはお住まいの自治体のごみ分別ルールを確認しましょう。
多くの地域では「プラスチックごみ」や「燃えるごみ」に指定されていますが、実際には細かい条件が付いていることもあります。
例えば、透明なPET製であれば資源ごみ、汚れていれば燃えるごみ、というように判断が分かれる場合もあります。
自治体の公式ホームページや配布される分別ガイドを確認し、不明点は環境課や清掃センターに問い合わせることが安心です。
汚れの落とし方と捨てる際の注意点
卵の殻や中身が付着していると回収ができない場合があるため、軽く水でゆすぐか、汚れを拭き取ってから処分するのが望ましいです。
汚れが取れないものは、燃えるごみに出すほうが適切です。
また、水洗いした後はしっかりと乾かしてから出すと、においやカビの発生を防ぐことができます。
特に集合住宅では湿ったままの排出がトラブルの原因になりやすいため注意しましょう。
資源ごみとして出せる場合と燃えるごみの場合
一部自治体では「透明なPET製卵パックのみ資源ごみ」として回収可能なところもあります。
必ずルールを確認し、指定に従って捨てましょう。
地域によってはリサイクルマークの有無をチェックする必要があったり、スーパーに持ち込む方法が推奨されている場合もあります。
燃えるごみとして扱う場合でも、他のごみと一緒に圧縮されやすいので安全に処理されやすい一方で、資源として活用できる機会を逃してしまうことになります。
できる限り分別に従い、環境に配慮した処理を心がけましょう。
卵パックを無駄にしない工夫

家庭でできる再利用アイデア
卵パックは細かく仕切られているため、ビーズやネジなど小物収納に便利です。
また、観葉植物の苗ポット代わりにも活用できます。
加えて、冷蔵庫内で薬味や調味料チューブを立てて整理したり、アクセサリーの一時置きにしたりと、工夫次第で生活の中の収納グッズとして幅広く使えます。
アウトドアやキャンプでは、調味料や小さな食材を分けて入れる容器としても役立ちます。
子どもの工作や収納に活用する方法
子どもの自由研究や工作に使えば、立体的な作品を簡単に作ることができます。
絵の具パレット代わりにもなるので、親子の遊び道具としても重宝します。
さらに、卵パックを組み合わせて動物や乗り物の形を作ったり、色を塗ってオリジナルの作品に仕上げたりと、創造力を育む教材としての価値もあります。
家庭で不要になったものを使うことで、リサイクル意識を子どもに自然に伝えることもできます。
環境への小さな貢献につなげる
卵パックをすぐ捨てるのではなく、一度再利用するだけでもごみの削減につながります。
家庭でできる「小さなエコ活動」として取り入れてみるのもおすすめです。
再利用の積み重ねは大きな資源の節約につながり、結果的に地域全体のごみ減量にも貢献します。
また、SNSなどでアイデアを共有すれば、周囲にもエコ活動の輪が広がっていくきっかけになるでしょう。
地域やスーパーの取り組み事例

コープやイオンでのリサイクル活動
一部のコープやイオンでは、透明なPET製卵パックを専用ボックスで回収する取り組みを行っています。
店舗によっては食品トレーと同じ場所に設置されていることもあり、買い物ついでに持ち込めるため利用者にとっても便利です。
さらに、会員向けにリサイクル活動を積極的に呼びかけたり、回収量を店舗ごとに掲示することで意識向上を図っている事例もあります。
こうした情報公開や啓発活動は、地域住民の参加率を高める大きな要因になっています。
一部店舗での専用回収ボックス設置
地域によってはスーパーが独自に卵パック回収ボックスを設置し、再生資源として活用している事例もあります。
例えば地方の中小規模スーパーでは、地域のリサイクル業者と連携し、集めた卵パックを園芸用のポットや梱包資材として再生する取り組みが行われています。
ただし、すべての店舗で行っているわけではないため注意が必要です。
設置されている店舗でも、汚れた卵パックや指定外の素材は回収できないため、利用する際には分別ルールをよく確認することが重要です。
成功事例から見える今後の可能性
こうした取り組みが広がれば、卵パックのリサイクルルートが確立される可能性もあります。
特に自治体とスーパー、リサイクル業者が連携して回収から再生までの仕組みを整えることで、効率的で持続可能なサイクルが生まれます。
すでに一部地域では、卵パックが新しいプラスチック製品として再生される成功事例も出ています。
環境負荷を減らす成功事例として、他地域にも広がっていくことが期待され、将来的には全国的な標準モデルとなる可能性もあります。
まとめ:卵パックとリサイクルの未来
卵パックが回収されにくいのは、素材の違いや衛生面、コスト面など複数の理由が重なっているからです。
とはいえ、一部地域やスーパーでは回収が始まっており、今後広がっていく可能性もあります。
加えて、環境問題への意識が高まる中で、企業や自治体が新しい回収スキームを模索する動きも見られています。
たとえば自治体とスーパーが連携して専用回収ルートを設けたり、リサイクル素材として利用できる製品開発が進められていたりと、少しずつですが改善の兆しも出てきています。
家庭でできるのは、正しい捨て方を守り、できる範囲で再利用すること。
卵パックを工作や収納、ガーデニングなどに役立てることは、ごみ削減につながるだけでなく、身近にエコを意識するきっかけになります。
小さな行動の積み重ねが、未来のリサイクル社会を支える力になります。
周囲とアイデアを共有したり子どもに教えたりすることで、世代を超えて環境への取り組みを広げることも可能です。