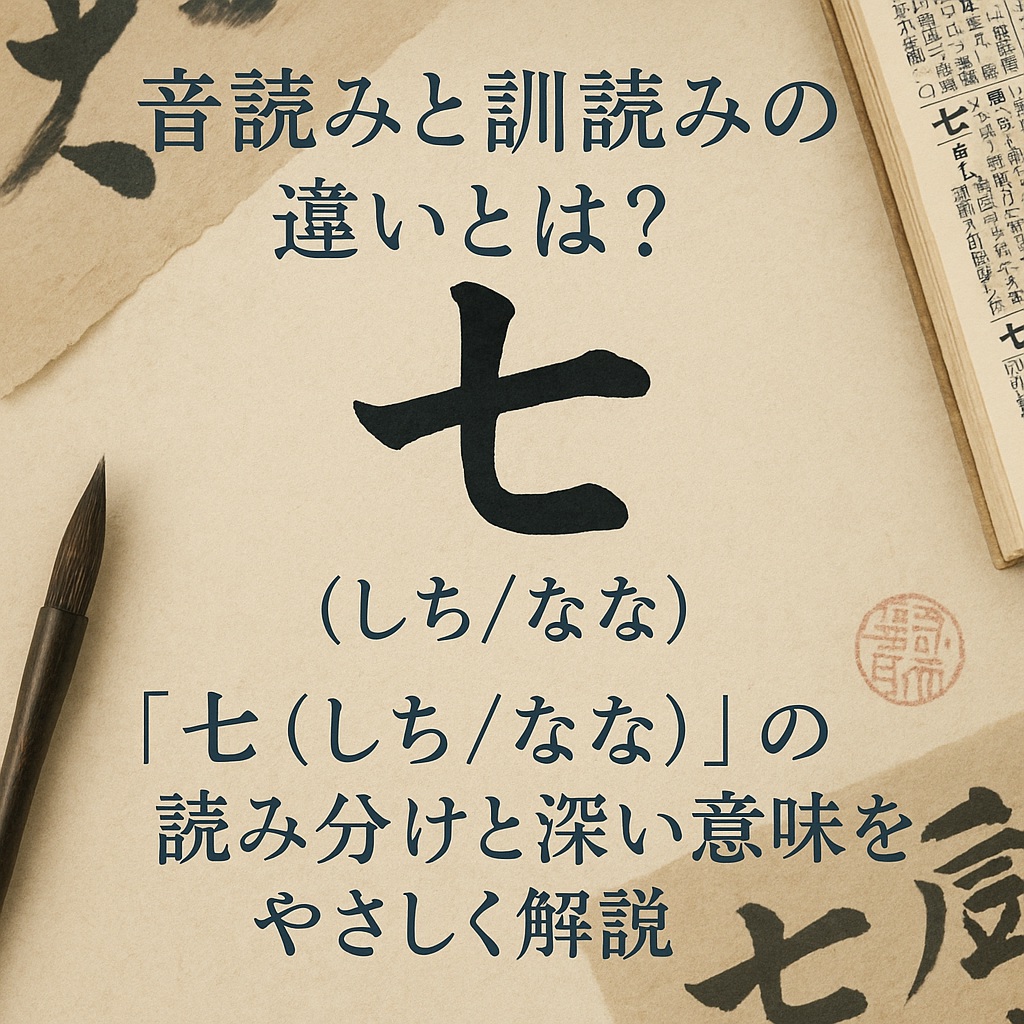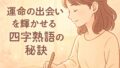漢字には「音読み」と「訓読み」という2つの読み方がありますが、なぜわざわざ読み方が分かれているのか疑問に思ったことはありませんか?
特に「七」という漢字は、”しち” “ひち” “なな” など読み方が複数あり、どれが正解なのか迷ってしまうこともありますよね。
この記事では、音読みと訓読みの基本から、「七」の正しい読み方の使い分け、さらに数字「七」に込められた意味まで、やさしく丁寧に解説します。
日本語に詳しくなくても大丈夫。初めて学ぶ方でも自然と理解できるよう、具体例を交えながらご紹介していきます。
音読みと訓読みとは?基本をわかりやすく解説

音読み:漢字が中国から伝わったときの読み方
音読みは、漢字が中国から日本へ伝わったときの”音”を元にした読み方です。
本来は中国語の発音に近い形を取り入れたものですが、日本語として発音しやすいように少し変化しながら使われるようになりました。
例えば「学校(がっこう)」「電話(でんわ)」「数字(すうじ)」のように、2文字以上の熟語には音読みが使われることが多く、特に学術的な言葉や新聞、ニュースで使われる語彙には音読みが目立ちます。
また、音読みは歴史的に時代ごとに伝来した発音が異なるため、「呉音」「漢音」「唐音」など複数の種類に分けられるのも特徴です。
訓読み:日本語の意味に合わせた読み方
一方、訓読みは日本人が昔から使っていた大和言葉に漢字の意味を当てはめた読み方です。
「山(やま)」「川(かわ)」「花(はな)」のように、自然や生活に身近な言葉は訓読みで読まれることが多く、日常会話でも頻繁に使われます。
訓読みは漢字一文字で完結した言葉として使われやすく、日本人の感覚に自然と馴染む読み方だといえます。
また、同じ漢字でも文脈によって読み方が変わることがあり、日本語の柔軟さや深みを表す特徴のひとつとなっています。
どっちを使う?音と訓の使い分けの基本ルール
音読みと訓読みの違いは、簡単にまとめると次のようになります。
- 熟語の場合 → 音読みが多い(例:経済、文化、自然など)
- 単語・日常表現 → 訓読みが多い(例:山、空、道など)
- 日本独自の言葉や表現 → 訓読み(例:心、光、夢 など)
- 固有名詞や地名 → 訓読みが多い(例:富士山=ふじさん)
ただし、例外もたくさんあり、完全なルールではありません。
どちらか一方だけが正しいというものではなく、文章全体の響きや意味の伝わりやすさによって読み方が選ばれることもあります。
この考え方を知っているだけで、漢字の読み方に迷ったときも自然に判断しやすくなります。
漢字「七」の読み方はなぜ多い?

「七」の音読み:シチとヒチの違い
「七」の音読みは「シチ」と「ヒチ」の2種類があります。
基本的には「シチ」と読むのが一般的ですが、実は日本語は場面によって読み方を柔軟に使い分ける特徴があります。
「七」は特に聞き間違いが起こりやすい数字の一つで、数字を読み上げる場面や口頭確認が大切な会話では「ヒチ」と発音されることが多くあります。
例えば、電話番号や伝票番号、試験の受験番号などを読み上げる際、「シチ」と言うと「イチ(一)」や「シ(四)」と聞き間違えられる危険があるため、「ヒチ」と発音して区別する配慮がされています。
このように、どちらか一方だけが正しいというわけではなく、聞き手に伝わりやすい読み方を選ぶことが大切です。
「七」の訓読み:なな・なのの使い分け
訓読みは「なな」「なの」があります。
どちらも日常生活で自然に使われていますが、実は使われる場面がきちんと区別されています。
- 「なな」→ 数を数えるときや数量を表すときに使う(例:ななつ/ななにん/ななこ)
- 「なの」→ 日付を表すときに使う特別な読み方(例:七日=なのか)
この使い分けは学校では軽く触れられる程度ですが、日本語を正しく美しく使うためにはとても大切なポイントです。
また、「七重(ななえ)」「七草(ななくさ)」のように、伝統文化にも訓読みが深く関わっています。
語呂や前後の音で変わる読み方(発音の連続性の影響)
日本語は、発音の流れや言いやすさをとても大事にする言語です。
そのため「七」は前後の音とのつながりによって自然に読み方が変化します。
例えば、「七百(ななひゃく)」「七匹(ななひき)」のように「なな」で読む方が発音しやすく、自然な響きになるため一般的です。
一方、スピーチやアナウンスなどで明瞭さが求められる場面では「しちひゃく」「しちひき」と読む場合もあります。
このように、「七」の読み方は音の流れ、聞き手への配慮、場面ごとの用途によって柔軟に変わるのが特徴です。
なぜ「七」は読み分けが多いのか?理由を解説

同音を避けるため(死・質との混同を回避)
「しち」という発音は「し(タヒ)」や「しつ(質)」と聞き間違えられることがあり、昔から縁起が悪い、あるいは誤解を招きやすい発音として避けられる傾向がありました。
特に日本では言葉の語感や響きをとても大切にする文化があり、不吉な意味を連想させる音は日常表現や商取引の場面で敬遠されることがありました。
このような背景から、状況に応じて読み方を柔軟に変える文化が自然と育まれたとされています。
また、仏教や縁起文化の影響で数字に意味を持たせる風習も生まれたため、同じ数字でも場面によって読み方を変える工夫が広く浸透していきました。
聞き間違い防止のため(電話・アナウンスでの使い分け)
電話番号や住所、確認が重要となる番号情報を口頭で伝えるとき、「しち」は「し(一や四)」と紛らわしいため誤解の原因になりやすく、正確さが求められる場面では「ひち」と発音することがあります。
特に航空管制や救急、鉄道、コールセンター業務などでは、数字の聞き間違いは重大な事故につながる危険があるため、より明瞭に聞こえる「ひち」が推奨されています。
この工夫は単なる言葉遣いの違いにとどまらず、情報伝達の安全性を高めるための重要な配慮として実践されてきたものです。
歴史的背景:江戸時代の商人言葉の影響
江戸時代には商人同士のやり取りで数字を正確に伝える必要がありましたが、市場の喧騒の中では声が雑音に紛れて聞き間違いが発生しやすかったため、数字に独自の呼び方を用いる「丁稚ことば」や「商人言葉」が生まれました。
その中で「七(しち)」は「ひち」と読むことで他の数字と区別しやすくなり、取引の場や算盤を使った商取引の文化の中で自然に広まっていったと考えられています。
このように、読み分けは単なる言葉の変化ではなく、日本の商習慣や生活文化と深く結びついた歴史的背景を持っているのです。
実用で迷う!「七」の読み方の正解一覧

日常でよく使う読み方まとめ(七時・七円・七日など)
「七」を含む日常表現で迷いやすいものを改めて整理してみましょう。
普段の会話やニュース、学校や仕事でのやり取りの中で頻繁に出てくる表現ですが、正しい読み方を知らないと誤解されたり、場合によっては恥ずかしい思いをしてしまうことがあります。
特に「七」は音読みと訓読みの両方が使われるため、使い方の傾向を覚えておくと安心です。
| 表現 | 正しい読み方 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 七時 | しちじ | 「ななじ」とは読まないのが一般的 |
| 七円 | ななえん | 金額は聞き間違い防止のため訓読みが多い |
| 七日 | なのか | 日付に使われる特別な読み方 |
| 七色 | なないろ | 虹の七色など日本文化でよく使われる |
| 七味 | しちみ | 「七味唐辛子(しちみとうがらし)」の略 |
迷いやすい読み方Q&A(七百/七回/七階など)
読み分けに悩みやすい例も詳しく見ていきましょう。この部分は実用的で、多くの人が疑問に感じるところです。
- 七百 → ななひゃく(一般的)/しちひゃく(やや固い表現)
- 七回 → ななかい(自然な読み方)/しちかい(強調や読み上げで使われることも)
- 七階 → ななかい(一般的)
- 七番 → ななばん(聞き取りやすい)
読み方が複数存在するのは、日本語が音の響きや聞き取りやすさを大事にする言語だからです。
読み方に迷ったときは「伝わりやすさ」を優先しましょう。
公式基準を確認(NHK・辞書・文化庁の見解)
NHKの『日本語発音アクセント新辞典』では、数字の読み方について「場面に応じた読み分け」を推奨しています。
また文化庁でも、言葉は状況や目的に応じて柔軟に使い分けられるべきだと説明しています。
つまり、「七」の読み方には絶対的な正解はなく、誤解を生まない読み方を選ぶことが重要だとされています。
「七」と助数詞の関係|読み方が変わる理由

助数詞によって読み方が変わる仕組み
日本語では、数える対象によって使う助数詞が変わります。
例えば「本(ほん)」「枚(まい)」「人(にん)」「匹(ひき)」などがありますが、「七」はこの助数詞との組み合わせによって読み方が変わることがあります。
これは、数をスムーズに発音しやすくするための日本語特有の音の調整です。
| 表現 | 読み方 | 備考 |
|---|---|---|
| 七つ | ななつ | 基本の数え方 |
| 七人 | ななにん/しちにん | どちらも使われる |
| 七本 | ななほん | 「しちほん」は不自然 |
| 七匹 | ななひき | 「しちひき」も可だが言いにくい |
| 七個 | ななこ | 日常会話ではこちらが自然 |
このように、助数詞との組み合わせでは言いやすさ・流れの良さが重視されます。
特に「なな」が多く採用されるのは、子どもや日本語学習者にもわかりやすい発音だからです。
読み方のコツと覚え方
迷ったときのコツはとてもシンプルです。
とはいえ、覚えていないと瞬時に判断できないこともあるので、ここで実践的な考え方を紹介します。
日本語の数字の読み方は柔軟で、厳密なルールというよりも「相手にとって聞き取りやすい読み方を選ぶ」という考え方が基本にあります。
そのため、次のポイントを押さえておくと場面に合わせて自然に使い分けができるようになります。
- 迷ったらまずは「なな」で読めばOK(最も安全で日常的な読み方)
- 公式の場・ビジネス・説明が必要なときは「伝わりやすさ」を優先
- 読み上げや放送(アナウンス)では「しち」も必要に応じて使用
- 数字を正確に伝える必要があるときは、聞き返しを防ぐ表現も有効(例:「七、ななの七です」など)
この3つ(+1つの補足)を意識しておけば、初対面の人との会話や仕事の電話対応など、少し緊張する場面でも迷わず使い分けることができます。
とくに数字は生活のあらゆる場面で登場するため、こうしたちょっとしたコツを知っておくと日本語への理解が深まり、言葉をより正確に使いこなせるようになります。
「七」に込められた文化的な意味

日本では縁起の良い数字
「七」は日本や世界各国で特別視される数字です。日本の伝統や文化の中にも、「七」を使った言葉や行事が数多く存在し、古くから生活の中に深く根付いてきました。
- 七福神(しちふくじん)…福を招く七柱の神様
- 七五三(しちごさん)…子どもの成長を祝う行事
- 七草粥(ななくさがゆ)…無病息災を願う行事食
- 七夕(たなばた)…願いごとを短冊に込める行事
これらはいずれも縁起の良い文化・行事に関係しており、日本人にとって「七」がお祝い・願掛け・節目を象徴する数字だとわかります。
数字にも意味を込める日本文化の中で、「七」は特に親しまれ、神聖で特別なものとして扱われてきたのです。
さらに民間信仰でも「七」という数字は重要視され、「魂は七日ごとに生まれ変わる」「七日ごとの法要」など、人生儀礼にも登場します。
このように、「七」は喜びだけでなく人生の節目や祈りにも関わる、日本人の心に深く根付いた数字だといえます。
世界でも愛される「7」という数字
実は、「7」は日本だけでなく世界中で特別視される数字です。
文化や宗教が違っても、多くの国や歴史に共通して「7」という数字が登場しているのはとても興味深い点です。
- 一週間は7日 → 古代バビロニア文明の天体観測に由来
- 虹は7色 → ニュートンが光の分散を7つに分類
- 音階は7つ(ドレミファソラシ) → 西洋音楽の基礎
- ローマの七丘 → 古代ローマ帝国の中心
- 古代インド哲学の7つのチャクラ
さらに、キリスト教文化圏では「7」は特に神聖な数字とされています。
- 創世記で「神が7日間で世界を創造」
- 「7つの大罪」や「7つの美徳」
- 「7回祈る」「7度の赦し」など聖書にも頻出
また、アラビア文化圏でも「7」は重要視され、幸運や守護を表す幸運数字(ラッキーナンバー)として扱われています。
カジノやスポーツの世界でも「7」は縁起の良い数字として人気があり、サッカーや野球で「7番」を背負う選手はエース格であることも多いですよね。
このように、「7」という数字は宗教・自然・科学・文化・芸術といった様々な分野で存在感を持ち、古今東西で“特別扱い”されてきた数字だといえます。
なぜ「七」は特別な数字なのか
「七」が特別視される理由は、文化的背景だけではありません。
実は人間の感覚や記憶に深く関係している数字だからとも言われています。
心理学の分野では、アメリカの心理学者ジョージ・ミラーによって提唱された「マジックナンバー7」という有名な理論があります。
これは、人間が短時間で処理・記憶できる情報の数は7±2(5から9の範囲)であるというものです。
例えば、電話番号やパスワードが7桁前後で構成されているのも、そのほうが人の脳にとって覚えやすいからだとされています。
さらに、「七」は区切りや循環を表す数字としても使われます。
1週間は7日で一区切りになり、仏教では人が亡くなった際に七日ごとに法要を営み49日で供養が一区切りとなります。
また、昔から物語の構成でも「七」はよく使われており、日本昔話の「七人の小人」や海外の「白雪姫」などにも登場します。
このように、「七」は人間の生活感覚や思考リズムに合いやすく、安定感や調和を感じさせる数字として無意識のうちに受け入れられているのです。
このような理由から、「七」は単なる数字以上の意味を持ち、縁起の良い数字、神秘的な数字、特別な数字として古今東西で愛され続けています。
「七」に関するよくある疑問(Q&A)
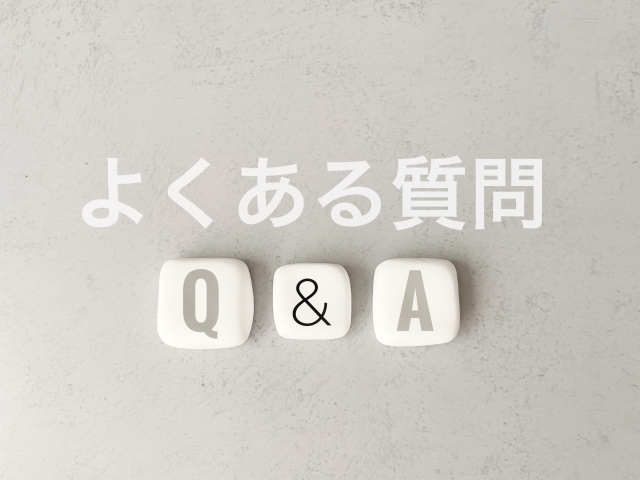
Q1. 七五三は「しちごさん」?「ななごさん」?
正解は「しちごさん」です。
「ななごさん」と読むのは誤りではありませんが一般的ではありません。
慣用表現では音のまとまりがよい読み方が定着しやすく、この場合は「しちごさん」が自然な響きを持つため広く使われています。
Q2. 七夕の正しい読み方は?「たなばた」or「しちせき」?
どちらも正しい読み方です。
- たなばた … 現代で一般的な読み方。日本の年中行事として定着
- しちせき … 中国の伝統行事に由来する古い読み方。歴史や古典ではこちらが使われることも
日常会話では「たなばた」が基本ですが、教養として「しちせき」も覚えておくと理解が深まります。
Q3. 七転び八起きはどう読む?
正しくは「ななころびやおき」と読みます。ことわざは訓読みが使われることが多いため、この場合も「ななころび」と読みます。「しちころび」と読むのは不自然とされます。
Q4. 七不思議の読み方は?
正しくは「ななふしぎ」と読みます。「しちふしぎ」も意味は通じますが、一般的には訓読みの「なな」が使われます。学校や民話、怪談などの文脈でも「ななふしぎ」という読み方が使われています。
Q5. 七草粥はどう読む?
正しくは「ななくさがゆ」と読みます。行事名や伝統的な言葉は訓読みが使われる傾向があります。「しちくさがゆ」や「ななぐさがゆ」は誤りなので注意しましょう。
他の数字漢字にも読み分けはある?
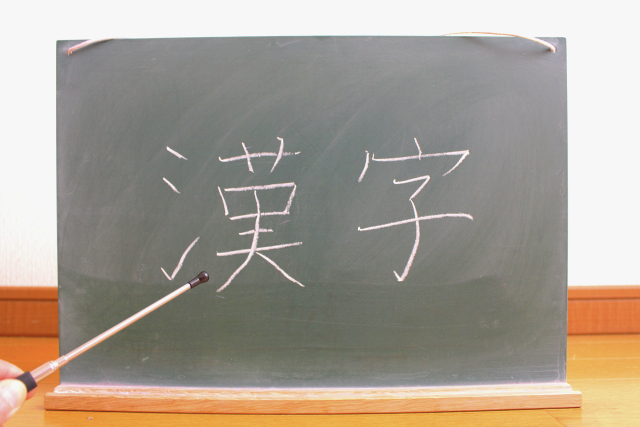
「七」だけでなく、ほかの数字にも読み分けがあります。
| 漢字 | 読み方 | 備考 |
|---|---|---|
| 一 | いち/ひと | 訓読みは主に和語表現に使われる |
| 二 | に/ふた | 助数詞と組み合わせで読み分けあり |
| 四 | し/よん | 「し」は「死」を連想し避けられることも |
| 九 | きゅう/く | 「く」は「苦」を連想し避けられがち |
このように、数字の読み方には日本語の文化や歴史が反映されており、場面に応じた読み分けが必要になります。
まとめ:音読みと訓読みを理解すると日本語がもっと面白くなる
「七」は読み方の多さから一見ややこしく感じられますが、その背景には長い歴史や文化的な理由があり、仕組みを理解するととても合理的で、日本語らしい表現の豊かさを感じることができます。
読み方を状況によって柔軟に使い分けるという日本語の特徴は、単に暗記ではなく“使いこなす”楽しさにつながっていきます。
- 「七」には音読み(しち/ひち)と訓読み(なな/なの)がある
- 読み分けは場面・聞き取りやすさ・語呂で決まる
- 文化的にも「七」は縁起や伝統に結びつく大切な数字
- ことわざや慣用句などにも多く使われる“意味を持つ数字”
このように、「七」という漢字を通して音読みと訓読みの関係を学ぶことで、日本語が持つ柔軟さや奥ゆかしさに気づくことができます。
音読みと訓読みを理解することは、日本語の奥深さを知る第一歩であり、ことば選びの幅を広げ、表現力を高めるきっかけにもなります。
ぜひ身近な言葉にも目を向け、「なぜこの読み方をするのか?」と考える楽しさを味わいながら、日本語の魅力をもっと深く感じてみてください。